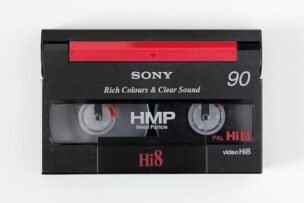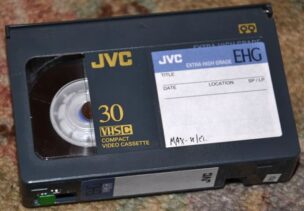24分率 読み:ニジュウヨンブンリツ
とは、
『全体を24とした、金の純度を表す国際的な規格』
概要
詳細≫
24分率とは、金の純度を 24を基準値として示す伝統的な純度規格を指す。
純金を「24」とし、そこから金以外の金属の割合によって「K18(18金)」「K14(14金)」のように示す方式が世界的に用いられている。
24という数値は、古代から中世ヨーロッパにかけて金細工が発達した文化圏で、24が合金比率の計算に都合が良い“割りやすい数”として実用的に採用され続けた歴史的背景に基づく。
現在も宝飾品や工業用途で広く使われている純度表示法で、K18なら純金75%、K24なら純金99.99%以上を指す。
語源
詳細≫
24「全体を示す基準値」分率「全体をどのように分けたかを示す割合」という構造から。
つまり「24を基準とした比率で純度を示す方式」という意味合いを持つ語で、宝飾や貴金属に関する分野で用いられる専門用語として定着している。