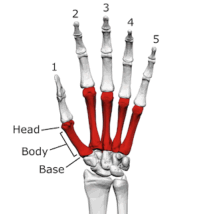杓子 読み:シャクシ
とは、
『汁物などをすくい取るための調理器具』
概要
詳細≫
「杓子」は、料理や配膳の際に汁物・飯・液体などをすくい取るために使う道具。
通常、柄が長く、先端がやや丸みを帯びた浅い皿状になっている。
木製・金属製・プラスチック製など素材は多様で、用途に応じて形状も異なる。
特に味噌汁や汁物を鍋からすくう時によく使われる。
同様の道具に「おたま」があるが、「杓子」はやや古風な言い回しで、和風の調理器具として語られることが多い。
例文
詳細≫
・母は味噌汁を杓子ですくって、椀によそった。
・この古い杓子は祖母の代から使われている。
語源
詳細≫
「杓」はすくうための道具を意味し、「子」は道具や器具を表す接尾語。「しゃく」は元々、竹などで作られたすくい器を指す漢語的表現で、これに和語の接尾語「し」がついて「しゃくし(杓子)」となった。