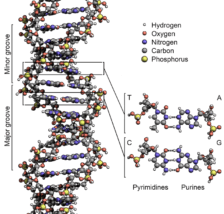粘菌 読み:ネンキン
とは、
『単細胞を基本としながら、生活環に応じて集合や融合を行い、子実体を形成する生物群』
概要
詳細≫
粘菌は、主に森林の朽ち木や落ち葉の上などに見られる微小な生物の総称で、植物・動物・菌類のいずれにも完全には属さない独特な存在として扱われてきた。
粘菌には性質の大きく異なる二つのタイプが含まれる。
一つは変形菌(真正粘菌)で、普段は単細胞が融合した巨大な多核体として振る舞い、条件が整うと色鮮やかな子実体を形成する。
もう一つは細胞性粘菌で、通常は個々に生活する単細胞のアメーバだが、餌が不足すると多数が集合し、多細胞生物のような構造体を作る。
このように、粘菌は単細胞と多細胞の境界に位置する生き方を示す生物として、生物進化の研究対象としても重視されている。
語源
詳細≫
粘「ねばる、粘り気がある」菌「微小な生物」を意味し、体が粘液状である特徴から名付けられた語。
菌と付くが、必ずしも真の菌類を指す名称ではなく、外見的特徴に基づく呼称である。
関連記事
画像:Philippe Garcelon(CC BY-SA 2.0)
出典元はこちら