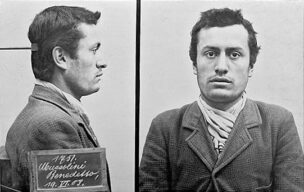Induced pluripotent stem cell 読み:インデューストプルリポーテントステムセル
人工多能性幹細胞 読み:ジンコウタノウセイカンサイボウ
iPS細胞 読み:アイピーエスサイボウ
とは、
概要
詳細≫
iPS細胞は、人や動物の体細胞(皮膚や血液など)に特定の遺伝子を導入して、多能性(さまざまな種類の細胞に分化できる性質)を持たせた人工の幹細胞。
再生医療や病気の研究、新薬の開発などに広く利用されている。
2006年に京都大学の山中伸弥らがマウスで作成に成功し、2007年にはヒトのiPS細胞も作られた。
臓器や組織の修復、難病治療の可能性を大きく広げた技術として注目されている。