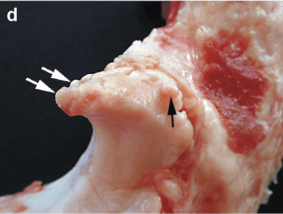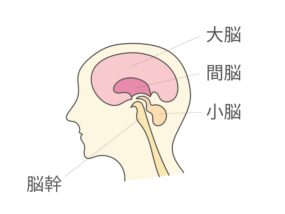画像:Rikke K Kirk, Bente Jørgensen, Henrik E Jensen(CC BY-SA 2.0)
出典元はこちら
医学
踵 (かかと/くびす/きびす)
踵 読み:カカト/クビス/キビス
とは、
『足の裏の後ろにある、丸く突き出た部分』
概要
詳細≫
「踵」は、足の後方にある部位を意味する言葉。
歩行の際に地面に接して体を支える部分である。
また、古くは「きびす」とも読まれ、「踵を返す」のように、方向転換や退去を表す比喩的な表現として使われてきた。
現代では「かかと」が一般的な呼称として定着している。
語源
詳細≫
「踵」は、もともと「きびす」と「かかと」という二つの読み方を持つ語。
「きびす」は上代から用いられた和語で、古語において「足の後ろの部分」を意味した。特に方向転換の動作を表す「踵を返す」に残っている。
「かかと」は後世に広く普及した呼び方で、「かか(掛かる)」+「と(所)」に由来するとの説がある。
つまり「体を掛ける部分」という意味合いを持つ。
両者は同じ対象を指すが、時代や文脈によって使い分けられてきた。
関連記事
iPS細胞 (あいぴーえすさいぼう)
Induced pluripotent stem cell 読み:インデューストプルリポーテントステムセル
人工多能性幹細胞 読み:ジンコウタノウセイカンサイボウ
iPS細胞 読み:アイピーエスサイボウ
とは、
概要
詳細≫
iPS細胞は、人や動物の体細胞(皮膚や血液など)に特定の遺伝子を導入して、多能性(さまざまな種類の細胞に分化できる性質)を持たせた人工の幹細胞。
再生医療や病気の研究、新薬の開発などに広く利用されている。
2006年に京都大学の山中伸弥らがマウスで作成に成功し、2007年にはヒトのiPS細胞も作られた。
臓器や組織の修復、難病治療の可能性を大きく広げた技術として注目されている。
語源
同義語
関連記事
Legionella (レジオネラ)
legionella 読み:れじおねら
レジオネラ菌 読み:れじおねらきん
とは、
『川や湖、温泉、土などに生息する細菌の総称』
概要
詳細≫
レジオネラは、レジオネラ属に分類される細菌の総称で、特に「レジオネラ・ニューモフィラ(Legionella pneumophila)」という菌種が知られている。
この菌は主に温水や冷却塔、加湿器、水風呂、循環式の浴槽などの水環境に生息しており、これらから発生したエアロゾル(細かい水しぶき)を吸い込むことで人に感染することがある。
感染すると、「レジオネラ症」と呼ばれる肺炎(在郷軍人病)や、軽症の発熱を伴う「ポンティアック熱」を引き起こすことがある。
特に高齢者や免疫力が低下している人にとっては重症化しやすく、衛生管理上の重大な注意が必要とされている。
語源
詳細≫
1976年にアメリカ・フィラデルフィアで開催された退役軍人(レジオン=Legion)会議に参加していた人々の間で集団肺炎が発生し、後に原因菌としてこの新種の細菌が発見されたことに由来する。
菌の名称「Legionella」は、この事件に関係する「American Legion(アメリカ在郷軍人会)」にちなんで命名された。日本語でもこの出来事に由来し、「在郷軍人病」という名称で知られる。
同義語
関連記事
大脳 (だいのう)
大脳 読み:ダイノウ
とは、
『脳の中で最も大きく、高度な認知・運動・感覚・言語などをつかさどる部分』
概要
詳細≫
大脳は脳全体の中で最も大きな部分で、人間の脳の大部分を占めている構造。
左右の大脳半球からなり、それぞれが前頭葉・頭頂葉・側頭葉・後頭葉といった複数の領域に分かれている。
大脳皮質(表面の灰白質)は、思考、判断、記憶、言語、感情、運動、感覚などの高次機能を担っており、人間らしい知的活動の中心となっている。
内側には大脳髄質(白質)や大脳基底核などの構造があり、自律的な運動の調整や感情の制御にも関与している。
進化的にも発達が著しく、人間の高度な精神活動の基盤となる重要な部位。
語源
詳細≫
大「大きい」脳「あたまの中にある神経中枢」という意味から。
つまり「大脳」は「脳の中でも特に大きく中心的な部分」を表す言葉で、医学・生理学・解剖学などで用いられる基本語。